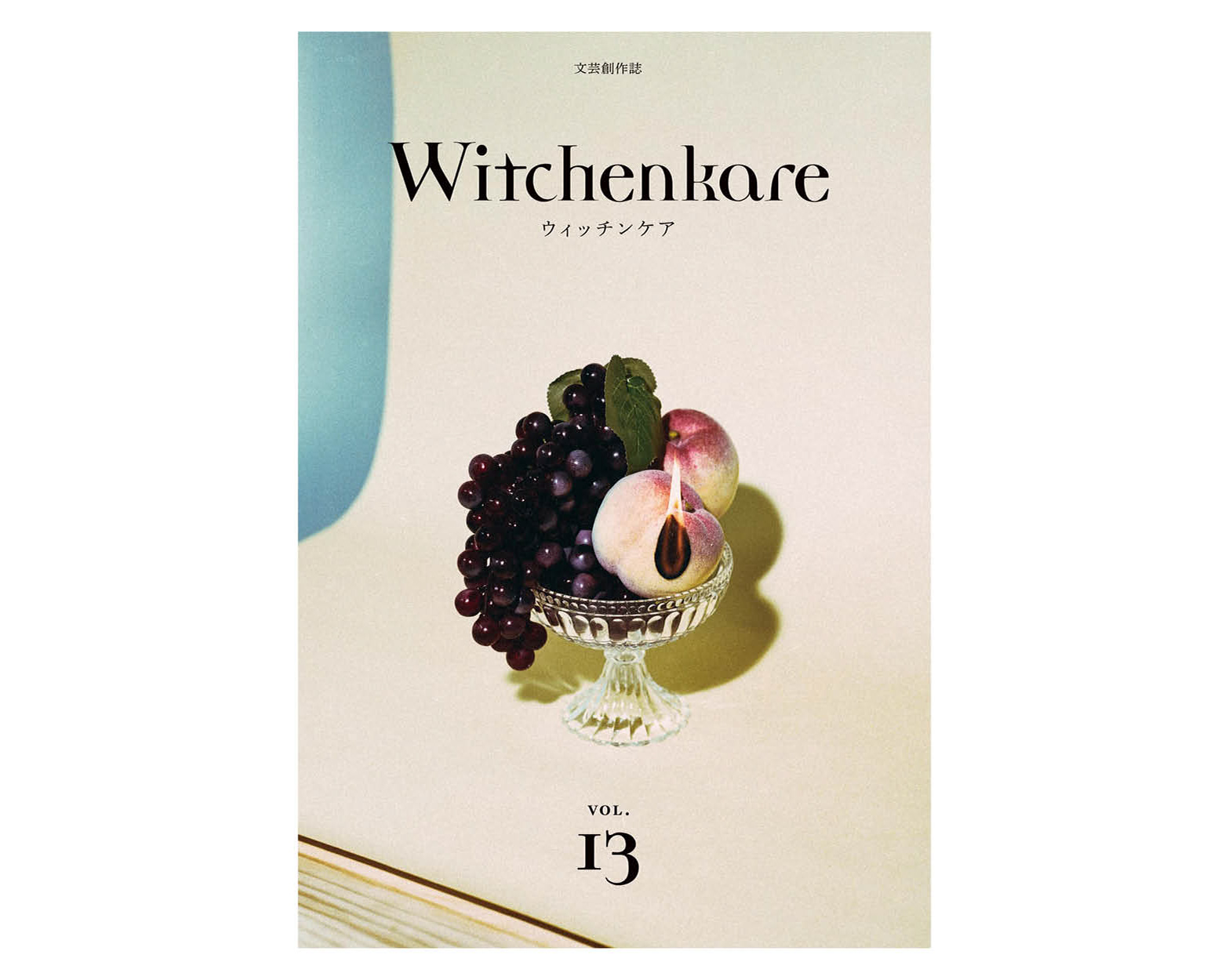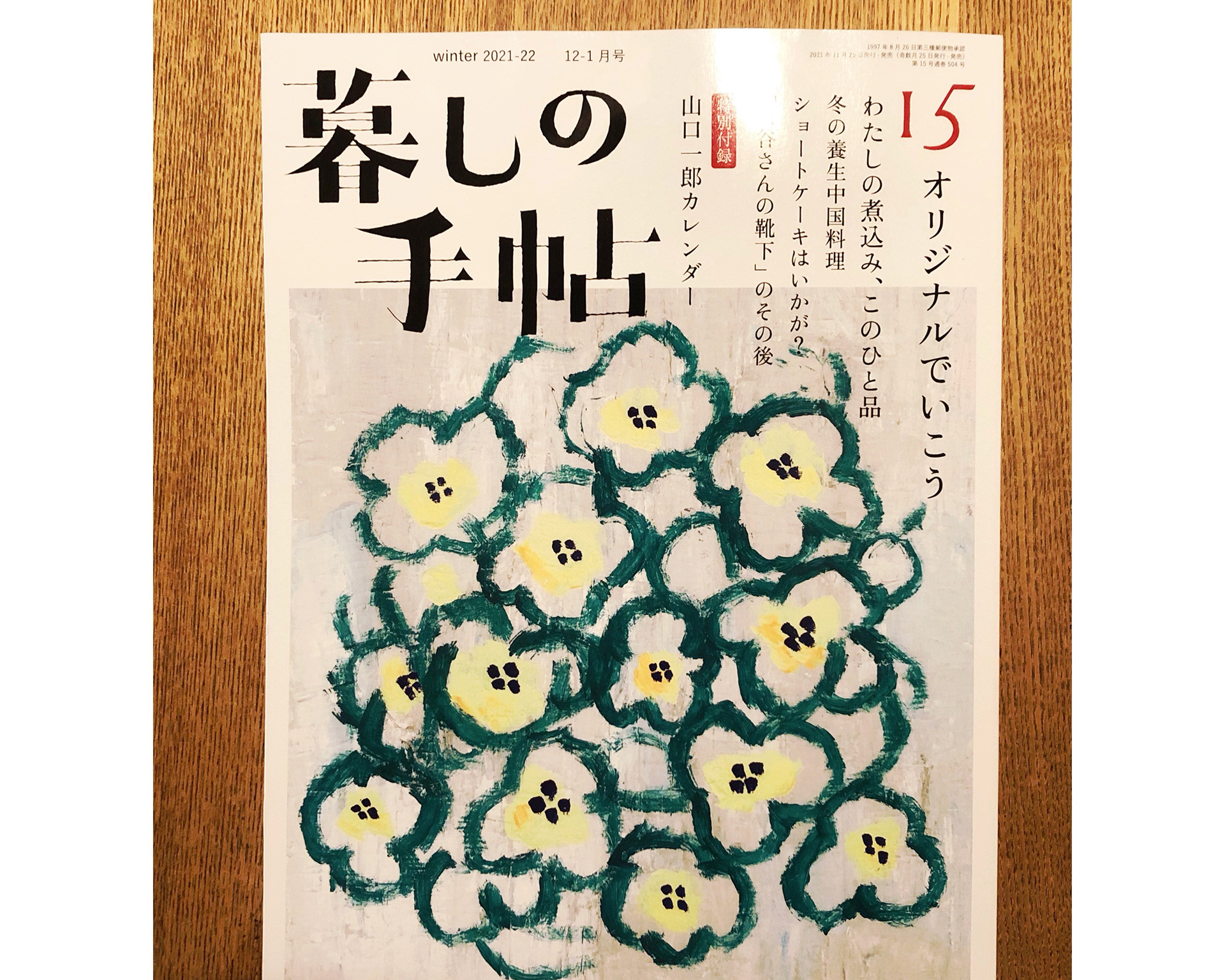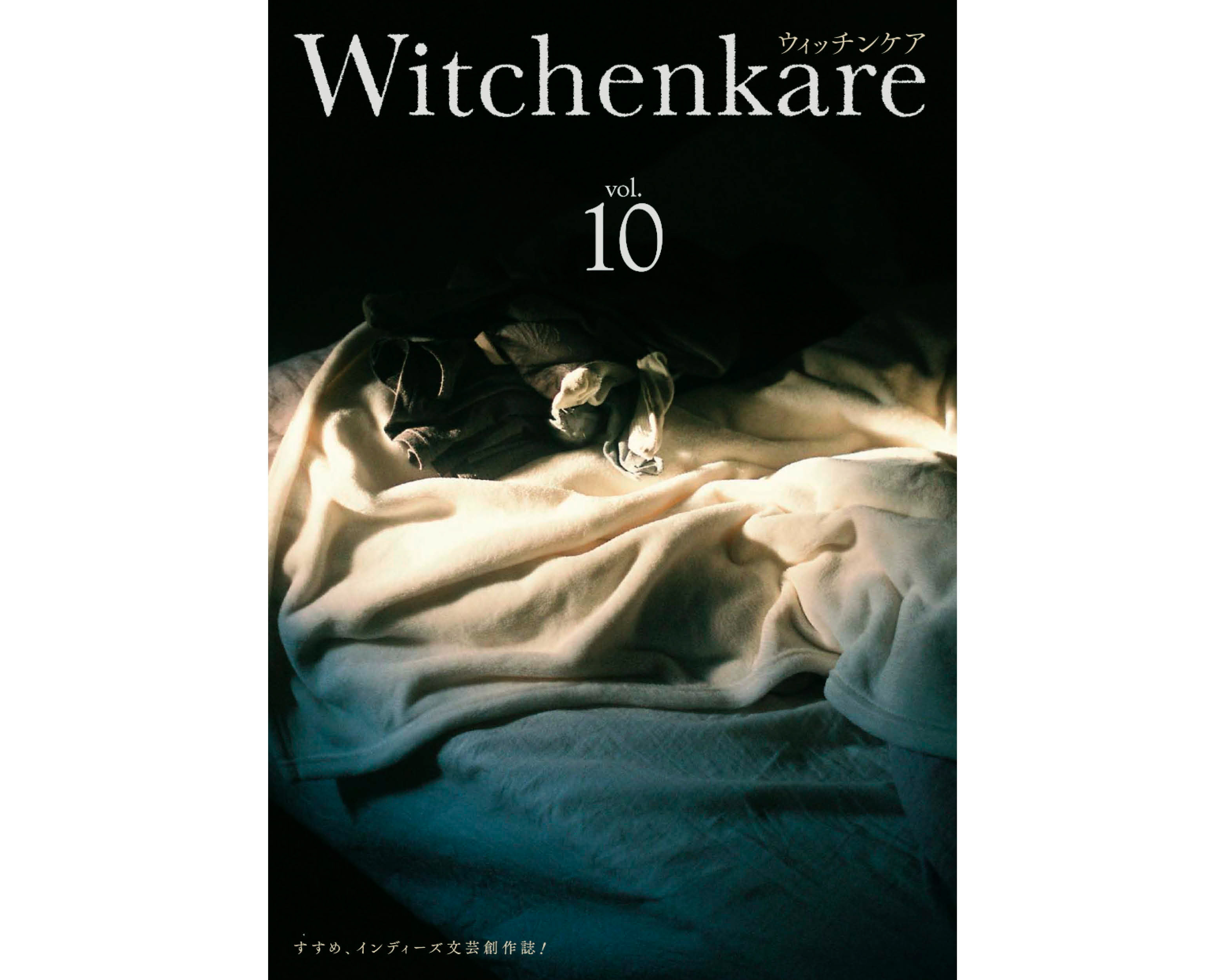2018年に発売された文芸創作誌「ウィッチンケア」にて、「荒木さんのこと」と題して
写真家・荒木経惟さんにまつわるエッセイを書きました。
荒木さんのこと
京都は烏丸御池のすぐ側に「新風館」という複合商業施設があった。元々は京都中央電話局として使用されたレンガ造りの豪奢な建物だったものをアパレルブランドやレストランなどの店舗を入れ改装し2001年にオープンしたのだった。一時期は京都の流行発信地としてその存在感を放っていたのだが、時代の波に追いやられ2016年にその役割を終えた。
当時滋賀で大学生をやっていた僕も京都に足を伸ばしてはこの新風館を訪れたものだ。小汚い格好をした僕がアパレルショップに用事などあるはずもなく、向かう先は3階にある書店。ここで日がな一日立ち読みをして時間を過ごすのが常だった。
その書店の一角に設けられた写真集コーナーで何気なく手に取ったのがアラーキーこと写真家・荒木経惟さんの「センチメンタルな旅 冬の旅」という写真集だった。赤い布地の表紙を開くと、髭面にサングラスの男性と、ウエディング姿の女性とがホテルの一室で並んで立っている写真から始まり、次ページには赤い字で「前略 もう我慢できません~」という手書きの文章があって、写真が続いていく。読んでいくとこの写真集が、写真家・荒木経惟さんと、妻・陽子さんとの愛と生と死の物語であることが分かる。
新婚旅行から始まった若い夫婦の愛の軌跡はやがて陽子さんの死によって終焉を迎えるのだが、最愛の人のその最期までを写真によって凝視し続け、物語にしたこの写真集を何の予備知識もなく開き、最後まで読んだ当時の僕は、書棚の前でむせび泣いた。涙を止めようと思えば思うほど溢れ出てきて、面識もない写真集の中の2人の中に流れる愛と、それを最期まで記録し続けた写真家の覚悟に震えた。写真を見て泣くなんて初めての経験だった。
それが荒木さんという写真家との初めての出会いだった。
それから数十年経って、数奇な巡り合わせで僕は今、写真家として生きている。
写真家となった最初、僕は古今東西様々な写真集を読み漁った。その中でも取り分け、荒木さんの作品と、饒舌な彼の口から放たれる写真論は、写真を撮ることとは何なのかを考える時の僕の指針のようなものになっていて、いつも心のどこかに荒木さんの言葉があった。
僕が初めて自費で写真集を作ろうと思ったのも、荒木さんがかつて若き電通カメラマンだった頃に自費で作った「ゼロックス写真帖」の存在に刺激を受けたからだし、写真集を作る上でのコンセプトや作った後でどうするかを考える上でも、彼の論理や実践方法を参考にした。
要するに僕は荒木さんから間接的に写真を学び、勝手にその方法論を参考にしながら自分なりの写真を構築していったのだった。
いつか会ってみて、話してみたい、できればこの人を写真に撮ってみたいと思うまでになった。
そしてその機会が2年前に訪れることになった。ある雑誌の企画で荒木さんを撮るカメラマンとして、指名を頂いたのだ。撮影当日までの2ヶ月間、彼の著書を改めて読み返し、何を話しながら撮るか何度も頭の中でシュミレーションを繰り広げた。しかし撮影前日に編集部から連絡がきた。
「荒木さんが体調不良で撮影できないって連絡があったんだよね。残念だけど、今回は見送ろう」
電話を切ってからじわりと滲み出る残念さと同時に、正直少しほっとした部分もあった。また機会があれば必ず会えるはずと思い直すことにした。
そしてその機会はまたすぐに訪れることとなった。
昨年京都で開かれた京都国際写真祭で荒木さんの作品が展示されることになったのだ。荒木さんだけでなく、世界の名だたる巨匠写真家や新進気鋭の写真家たちの作品が出展されるこの写真祭において、僕の作品も展示されることとなったのだ。
その作品とは、宮崎県に住む88歳の僕の祖母と23歳の看護大学生だった従兄弟の生活を綴った「Falling Leaves」という作品だった。
ずっと共に生活していたこの2人を写真に収めていた僕は、そう遠くない将来やってくるであろう祖母の死をもって完結させるつもりだった。しかし、その考えは意外な展開によって覆されることになる。ある日突然、従兄弟が失踪し行方をくらましたのだった。探せども探せども彼の消息を掴むことができなかった。そして失踪して1年後に彼は山中で発見されることになる。還らぬ姿となって。自死だった。
その衝撃と悲痛さを抱えたまま祖母も翌年逝った。
2人がこの世からいなくなって残ったのは、在りし日の彼らの姿が写った幾葉もの写真たちだった。僕はそれらをまとめて2人が生きた痕跡を残すつもりで、物語にしようと試みた。
試みたはいいが、しかしその過程は相当に苦痛を伴うものだった。写真の中に写っている2人はまるで今日も生きているかのように躍動し、幸せな時間を過ごしていた。だから余計に胸を抉られるような気持ちになった。身内に起こった出来事を客観的な視線を保ちながら作品を作ることなど到底不可能に思えたし、一体この物語をどのように構成すればいいのか、検討もつくはずがなかった。これまで作ってきたどんな作品とも違う手触りと重さに僕は途方に暮れるのであった。
そんな時、自室の書棚から引っ張り出して繰り返し見たのが、荒木さんのあの写真集だった。
妻との愛と生と死を綯い交ぜにした作品を世の中に発表した荒木さんの当時の状況を想像し、そこに自分を重ね合わせてみることで、僕が祖母と従兄弟の写真を世の中に出す意味は何なのかを考えるヒントにしたかったのかもしれない。いや、それよりも近親者の死というある種タブー的なこの作品を発表することでつきまとってくるであろう批判や非難に対し僕がどう受け止めるのか、その覚悟の在り方に対して、写真家としての矜持を荒木さんの言動から見出したかったのかもしれない。
どっちにしろ、当時の僕は迷いの中に居たと言っていい。迷いながらもやはりどこか一条の光を求めて、写真集だけでなく、荒木さんがあの作品を作り上げた当時の映像や、著書なども読み漁った。
その中で荒木さんはこう言っている。
「これは俺自身のためのものなの。なんといっても第一の読者は自分なんだから」
当時、作品を発表したばかりの荒木さんはきつい批判を受けたようだった。「不謹慎」「あなたの妻の死なんて他人には関係ない」「不遜な写真」。しかし、荒木さんは「自分自身のため」とそれらの言葉を一蹴し、妻・陽子さんへの愛を写真作品へと昇華したのだった。とは言うものの、
「俺の写真家としての第一ラウンドはこれで終了したよね」
との言葉が物語っているように、きっと相当な痛みと悲しみを伴ったに違いない。だからこそ観るものに強く訴えかける何かが内包されたのだろう。最愛の人を写真によって見つめ続けた写真家の、最上の愛の形がこれしかなかったのだろうと思う。
そうなのだ、結局僕は僕のこの作品を誰のために作りたいのか、どんな物語を編み上げたいのかという最も大切な部分が判然としていなかったのだ。
そのことが荒木さんの足跡を辿る旅の中で、僕の心の中を覆っていた霧が少しづつではあるが晴れていくのだった。
「誰になんと言われようが僕は必ず作品にする。」
それから僕は色々な人の手を借り、試行錯誤しながら何とか作品を作り上げ、京都国際写真祭で初めて発表することになったのだった。
しかし、同祭で荒木さんに出会うことはなかった。やはり体調不良ということで京都まで来られなかったのだ。
ただ、現実とは奇怪なもので、僕が展示した場所というのが、かつて荒木さんの作品を初めて手にし、出会ったあの「新風館」だったのだ。
今やコンクリートむき出しの廃墟となってしまったそこに僕の作品が展示され、多くの人が訪れ、涙する光景を見ていると、十数年前に自分がこの場所で荒木さんの写真集を見て泣いた光景と重なり、何とも不思議な運命を感じるのであった。いつか荒木さんにこの話をしに行きたい。